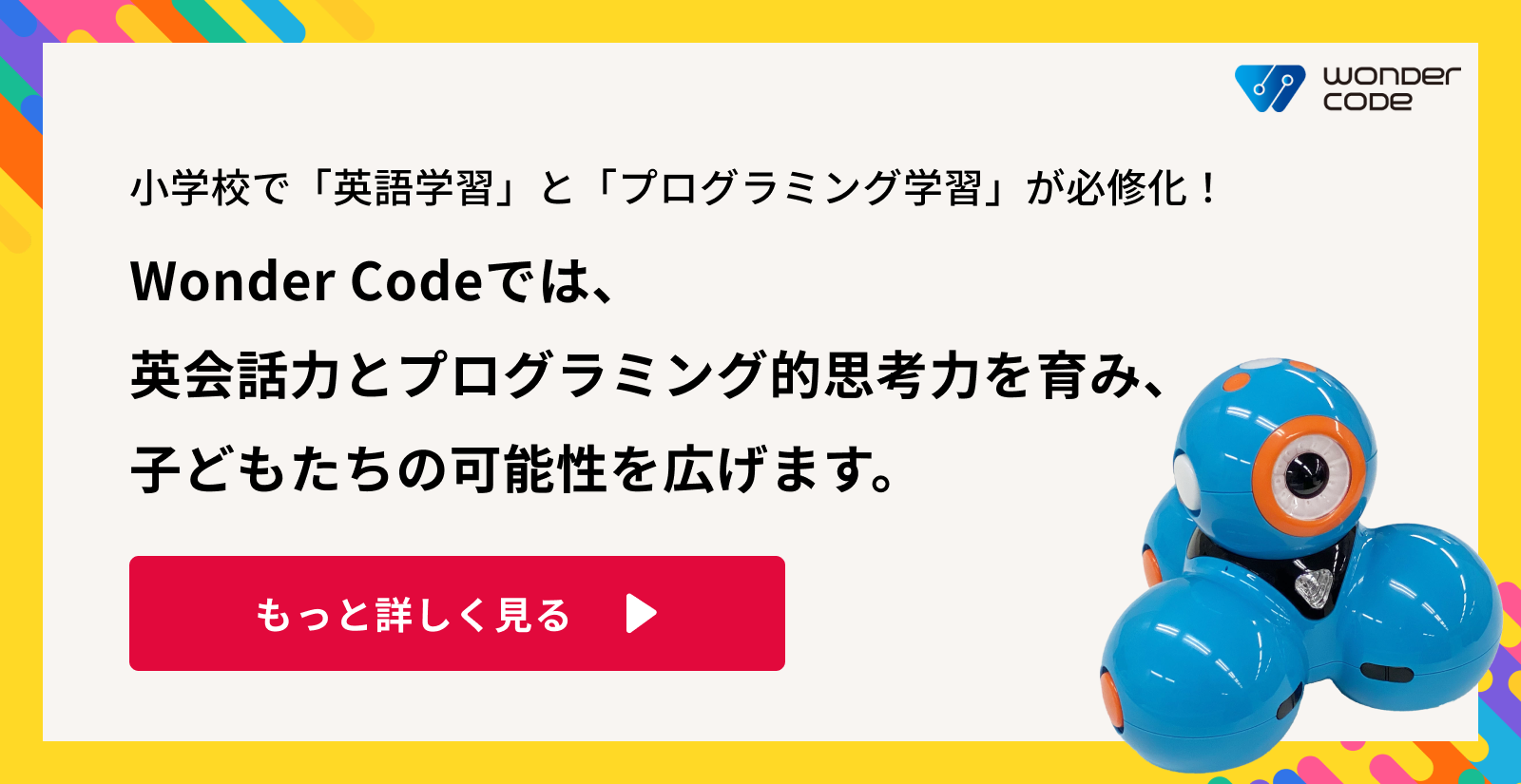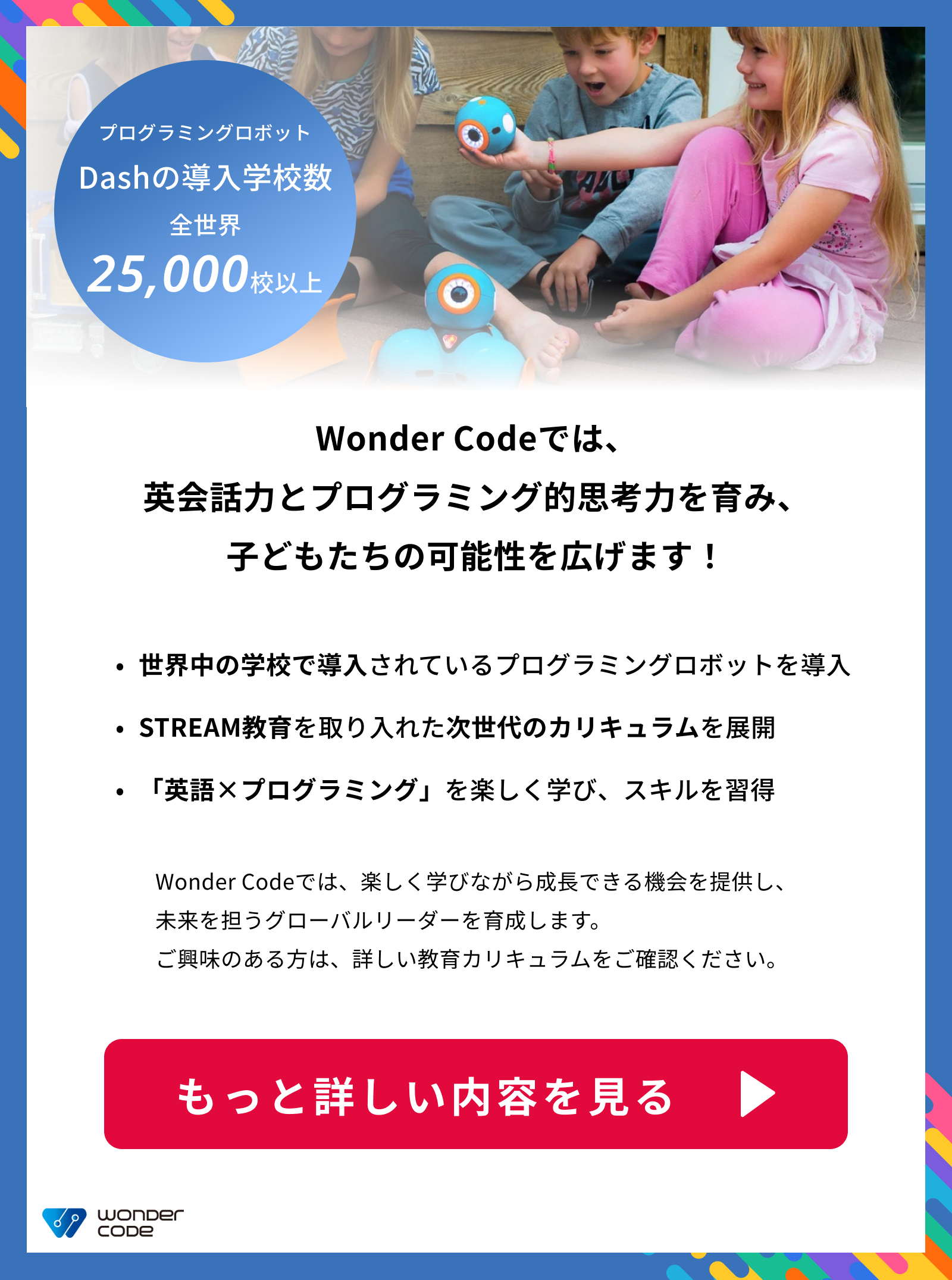【この記事の目次】
子どもの理解力を高めるために必要な「聞く力」とは?

私たちは日々、他者とコミュニケーションを取りながら生活しています。学校の勉強も社会に出た後の労働も、コミュニケーションなくしては成り立ちません。円滑な人間関係の構築のためにも、お互いの価値観を認め合い、言葉に耳を傾ける意識が求められます。
人の話を聞く力の有無は、子ども時代から影響を及ぼします。聞く力が高い子どもは同じ授業を聞いていても学習効果が高く、周囲とも良好な人間関係を築きやすいでしょう。聞く力は、家庭における日々のコミュニケーションで養うことが可能です。
今回は、子どもの聞く力について解説していきます。聞く力が足りない子どもの注意点から、家庭でできる聞く力を身につける方法などを紹介していきます。子どもの人生をより生きやすいものにするためにも、できる限りサポートしていきましょう。
聞く力がない・足りない子どもの注意点

まずは、聞く力がない・足りない子どもの注意点について解説します。もちろん、どの子どもにも生まれ持った個性や性質があり、そのすべてが平等に尊重されるべきものです。もし我が子に聞く力が不足していると感じる場合でも、子どもの個性を否定するのではなく、より生きやすい選択肢を提示するためにも注意点を学んでいきましょう。
コミュニケーションに不備が生じやすい
聞く力が足りない子どもは、コミュニケーションに不備が生じやすい傾向にあります。大人同士の関係でも、自分の話をあまり聞いてくれない相手には不満を抱いてしまうことがあるでしょう。子どもの関係性でも同様のトラブルが起こり得ます。
例えば、相手の話に耳を傾けずに自分の話ばかりしてしまったり、相手の話を誤解して受け取ってしまったりすることなどが挙げられます。一見すると明るくコミュニケーションを取れているように見えても、相手の言葉の本質を受け取れていないため、相互理解から遠のいてしまうのです。
問題文やテキスト内容を間違えて理解しやすい
子どもの聞く力が足りていないと、学校の授業で問題が生じる可能性があります。例えば、問題文やテキストの内容を間違えて理解してしまったり、間違った知識を信じ込んで固定観念を抱いてしまったりすることが考えられます。
子どもなりに真面目に授業を受けているのにもかかわらず、テストの成績になかなか反映されなかったり、同じ授業を聞いているはずなのに、周りの子よりも成績が伸びなかったりすることもあるでしょう。
テストという限られた時間の中では、問題文を正しく読み解ける能力は結果に直結します。間違えた知識のまま中・高校生になってしまい、慌てて勉強し直す必要に駆られることがあるかもしれません。
努力の方向性を間違えやすい
聞く力が足りない子どもは、他者の言葉の本質をつかめずに間違った受け取り方をしてしまいがちです。例えば、自分にとって都合がよい意味で受け取ってしまったり、面倒な言葉には耳を塞いでしまったりすることがあります。子どもに悪意があるわけではなく、無意識のうちに嫌なことは聞かない姿勢を取ってしまうのです。
その結果、勉強やスポーツなど、あらゆる分野で努力の方向性を間違えてしまう可能性があります。「一生けん命頑張っているのに報われない」という気持ちは自己肯定感を失わせ、コンプレックスが膨らみ、夢や目標を諦めてしまう心理につながるでしょう。
子どもの聞く力を養う5つの方法
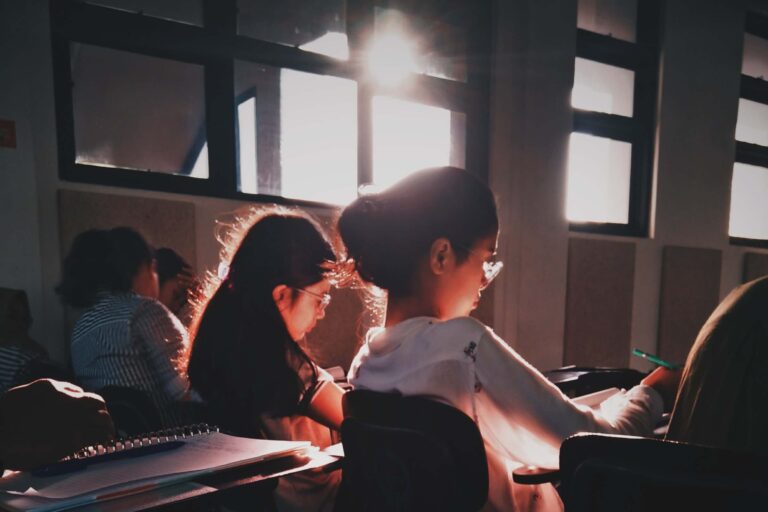
ここでは、子どもの聞く力を養うために必要な方法を5つご紹介します。子どもの聞く力を養うためには、コミュニケーションの楽しさや奥深さに気づいてもらうことが必要です。表面的な言葉だけではなく、言葉の裏に秘められた本質的なテーマに気づいてもらうためにも、根気強く対話していきましょう。
子どもが興味を持つ話題で例える
子どもの聞く力を養うためには、子どもが興味を持つ話題で例えることをおすすめします。例えば、子どもが好きなアニメのキャラクターで人間関係を例えてみたり、ゲームの操作や進め方と実生活をリンクさせたりするような関わりがよいでしょう。
実際の所、アニメ・ゲーム・漫画など子どもが好むコンテンツには、教育のヒントが多く隠されています。子どもが熱中している娯楽を保護者も一緒に楽しみつつ、共通の話題を介して家庭教育に活かしていきましょう。
子どもの話にもしっかりと耳を傾ける
子どもの話にしっかりと耳を傾けることは、子どもの中のコミュニケーションへの欲求を引き出します。保護者になかなか自分の話を聞いてもらえない子どもは「聞いてほしい」という気持ちだけが高まり、相手の話を聞く余裕がなくなりがちです。
「自分の話を聞いてもらえている」という安心感と親への信頼を抱けるからこそ「相手の話にも耳を傾けてみよう」という気持ちになるのです。子どもの聞く力を養うためには、傾聴をした上で子どもの精神的な安心感を育んでいきましょう。
しかるときは短時間で要点だけを伝える
子どもでも大人でも、嫌な言葉や都合が悪い話題には耳を塞ぎたくなるものです。とはいえ子どもとの生活は、しかったり注意したりすることの連続ですよね。保護者の中には「一日何回怒鳴ったりしかったりすればいいの?」と悩んでいる人も多いでしょう。
子どもの聞く力を育てるためには、簡潔な言葉で要点だけ絞って伝えることが大切です。子どもにとって親のしっせきの時間はストレスになります。また、話が長引くほど子どもの集中力や注意力がなくなるため、言葉の本質が伝わらないものです。論理的な言葉や文脈を用いて、本質だけを伝えるよう心がけましょう。
伝言ゲームや連想ゲームを取り入れる
子どもの聞く力を育成するためには、伝言ゲームや連想ゲームを取り入れることを推奨します。伝言ゲームも連想ゲームも、相手の話をしっかりと聞いていなければ勝てません。そのため負けず嫌いの子どもには特におすすめの方法です。
伝言ゲームでは、相手の言葉を都合よく解釈せず言葉通りに受け取る力が磨かれるでしょう。また連想ゲームは、一つの言葉から複数の意味やイメージを広げる訓練になります。絵が得意な子であれば、イラストを用いた伝言・連想ゲームに発展させても一つの方法です。
創作物に触れ、感想を伝え合う
聞く力は、伝える力とも深い関係があります。親子で同じ創作物に触れ、お互いにどのような感想を抱いたのか意見交換してみましょう。その際に「お互いの感性や感想を否定しない」と「相手が話しているときは言葉を被せない」をルールに設けると効果的です。
自分の考え方だけが正しいわけではないことや、人間は一人ひとり違う感性を持っていることを自覚できれば、視野が広がり聞く力も育まれていきます。創作物のジャンルは、無理に大人っぽいものにする必要はありません。子どもが好きなものに限定することで、対話への集中力を維持できるでしょう。
理解力を高めるために必要な能力

子どもの聞く力を養うためには、相手の言葉の本質を知るための理解力が求められます。ここでは、子どもの理解力を高めるために必要な能力をご紹介します。基礎的な理解力は、社会に出たときにあらゆる職業で求められるスキルです。必要な能力を総合的に伸ばしながら、子どもの人生や人間関係の構築をサポートしていきましょう。
読解力
読解力は文章を読む速さだけではなく、文章の意味を正しく理解する能力も含まれます。ストーリー性の高い小説は登場人物の行動の意味や心理を理解する必要があるため、読解力を上げるために読書の習慣を取り入れてみましょう。
一日10分程度でもいいのです。親子で本を読む時間を作って、子どもが好みそうなライトノベルを与えてみましょう。一緒に本屋に行って子ども自身に小説を選んでもらうのも効果的です。
想像力
相手の言葉の意味を正しく理解するためには、言葉の表面だけではなく本質をつかむための想像力が必要です。水平思考ゲームや推理小説などを取り入れて、楽しく想像力を膨らませていきましょう。
特に水平思考ゲームは、正解に近づくために与えられた情報から想像力を広げる必要があります。相手から提示される情報を聞き逃さないための傾聴力も養われますので、聞く力に求められる総合的な能力が育まれるでしょう。
忍耐力
相手の話をしっかりと聞いて理解するためには、一定の忍耐力が必要です。忍耐力が乏しい子どもは、相手の言葉を途中で遮ってしまったり、苦手な話題をすぐにすり替えたりしがちです。
まずは「相手の話を最後まで黙って聞く」という訓練から始めてみましょう。コミュニケーション自体に苦手意識を持たれてしまわないように、子どもに寄り添った言葉・話題選びを心がけてくださいね。
論理的思考力
論理的思考力を養うことで、相手の言葉から本質を推測する能力が身につきます。情報同士をつなぎ合わせる力は理解力につながり、普段の人間関係の構築にも大きなメリットを与えるでしょう。
子どもの論理的思考力を鍛えるためには、算数の勉強だけではなくプログラミングやボードゲームなどもおすすめです。論理的思考力の育成に特化したゲームを調べ、子どもの特性に合わせた方法を家族で取り入れてみましょう。
子どもの理解力を高めるなら『Wonder Code』で楽しく学ぼう!

今回は、子どもの聞く力の必要性や家庭でできる育成方法などをご紹介しました。聞く力を養うためにはコミュニケーションが基本となりますが、闇雲に対話の量を増やすだけでは子どもはうんざりしてしまいます。
自分の話を聞いてもらえている安心感や、コミュニケーション自体への楽しさを抱けることで、聞く力は養われていきます。リアルなコミュニケーションだけではなくフィクションの創作物も取り入れながら、楽しく聞く力を伸ばしていきましょう。
Wonder Codeではプログラミングを通して、聞く力を養うために必要な読解力・想像力・忍耐力・論理的思考力を総合的に育成できます。ぜひこの機会に、無料体験教室や資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。