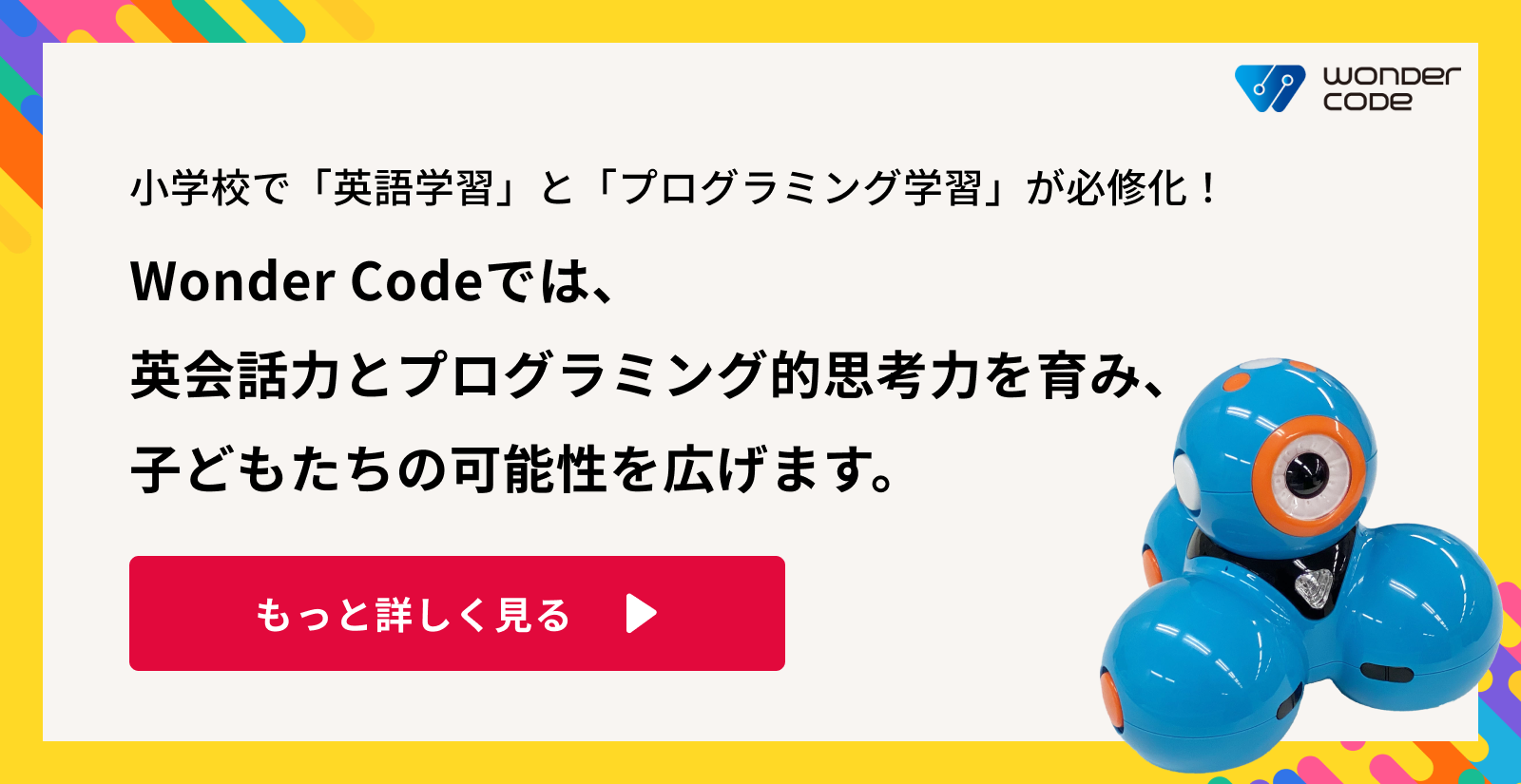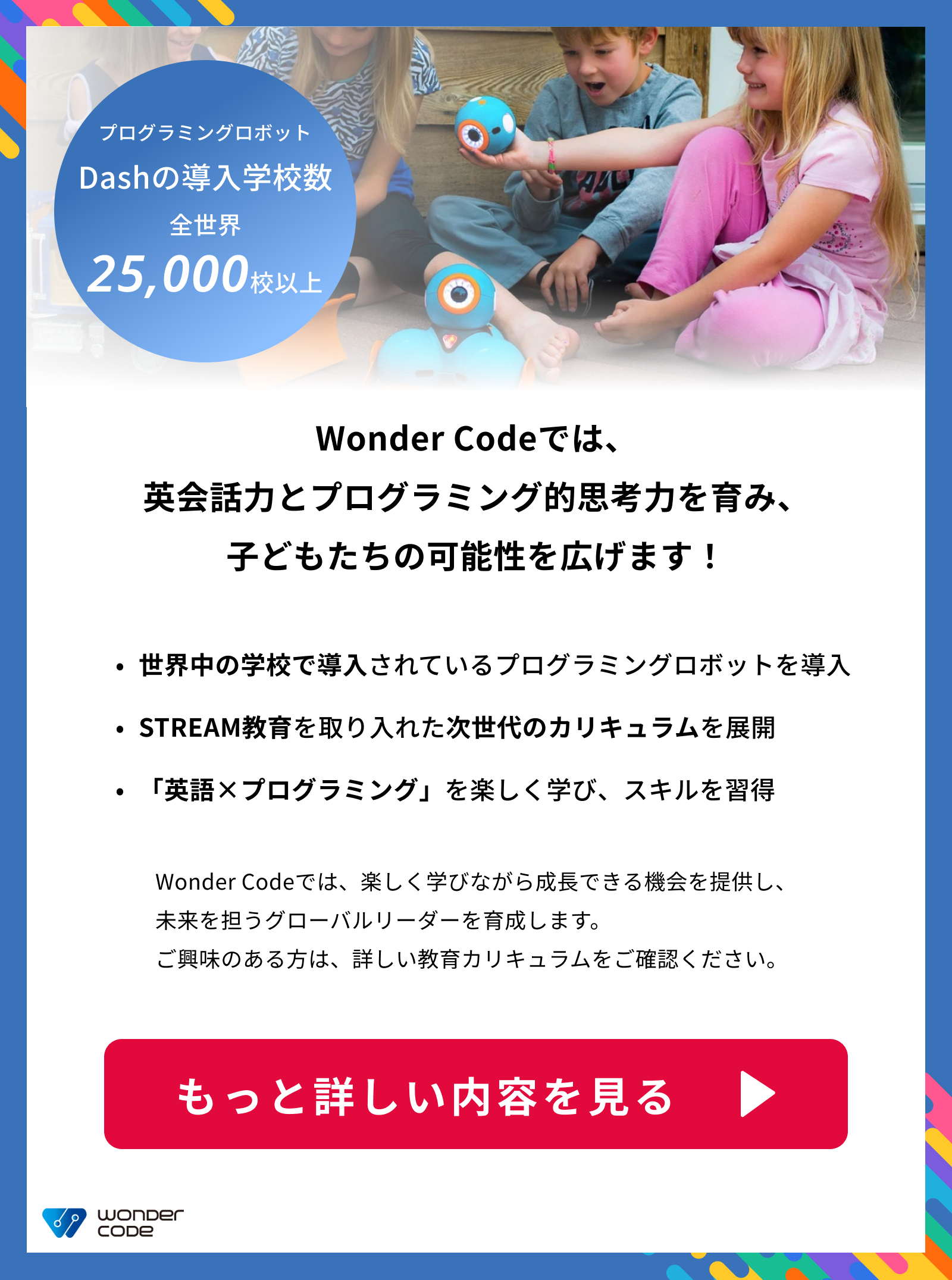【この記事の目次】
子どもの感性を磨いて、豊かな心を養ってもらいたい…

昨今はAIテクノロジーの発達が著しく、未来を予測するのは難しくなっています。こうしたなか、課題を見つけたりアイデアを創出したりする力が求められており、その基盤になるのが感性といえるでしょう。
感性とは、例えば自然の変化の機微を感じ取りながら表現活動を行う力を指します。また、人の話を共感的に理解しスムーズにコミュニケーションをとるのも感性豊かな人の特徴です。
「傷つきやすい」といったデリケートな側面があるとはいえ、保護者が感性を育てる姿勢でいた方が子どもの可能性を伸ばしやすいでしょう。
今回の記事は感性を育てる大切さがわかる内容になっています。「子どもの感性とは?」の問いに対する答えや感性を磨く重要性、育成方法についてご紹介します。
感性の意味とは

感性とは、ある出来事や事象に対して深く感じ取った内容を自分らしく表現する力を指します。また、感性は人との関わりを円滑にしたり芸術的な才能を開花させたりする際に必要な力といえるでしょう。
感性と似た言葉に感受性があり、両者の違いは下記のように区別されます。
- 感受性:感情を生み出す力
- 感性:感情を具現化する力
「感受性」とは朝陽が水平線から昇るのを見て「きれいだなあ」と感じる様子を指します。「感性」とは「きれいだなあ」と思った気もちを絵画や詩に表現する様子を示すこととらえてみてください。
また、感性における重要な視点として「自分らしさ」が挙げられます。たとえば同じ朝陽を見ても“Aさんは太陽の色、Bさんは全景の美しさに感動する”など個人によって違いがみられます。
このように感性とは人によって異なる様相を見せるものを指し、ある意味「個性」を感じさせるのが感性だといえるでしょう。
豊かな感性を持つ子どもの6つの特徴

感性とは、心に深く刻まれる感動を自分らしく表現することを指します。
豊かな感性には研ぎ澄まされた五感が必要になるでしょう。その理由は、感受性が鋭ければ鋭いほど多様な情報を得られアウトプットにつなげやすいためです。
そのほか感性のある子どもは、固定観念に縛られず多面的な見方で物事をとらえたり、人とのやり取りをスムーズに行ったりします。ここでは、感性が豊かな子どもの特徴として6つ紹介します。
固定観念にとらわれない
固定観念とは型にはまった見方や考え方を指します。豊かな感性を持つ子どもは、固定観念にとらわれず自分の感じるままに行動できるのが特徴です。
感性が豊かであればあるほど、双方向あるいは多方面から見て解決しようとします。このため多様なアイデアを創出し、ほかの子どもとは異なる発想で芸術面でのセンスを見せることでしょう。
また、豊かな感性を持つ子どもは柔軟に物事を考えられるため、ありとあらゆる事象から学び取る力も優れています。
情報を五感で感じ取る
感性が豊かであると五感をフル稼働させて物事をとらえます。五感とは、視覚や聴覚、嗅覚、触覚、味覚の5つの感覚を指します。たとえば、次のような行動を示す子どもは感性豊かな子どもです。
- 道端に咲くスミレを見て「小さいけれどきれいな紫だね」
- 街に流れる音楽を聞いて「なんだかスキップしたくなるよ」
- 親子で訪れた店舗に入って「オレンジの香りがいいねえ」
- 洋服を触って「なんだかお母さんに抱っこされているみたい」
- クリームソーダを飲んで「クリームがシュワッとする感じが好き!」
このように些細な出来事に対しても、感覚をとぎすませて子どもらしく表現する場面が見られれば、その子どもは感性豊かだといえるでしょう。
物事の背景や文脈を想像できる
「物事の背景や文脈を想像できる」とは、物事の見えない真実や秘密などを推測できる力を指します。
豊かな感性を持つ子どもは、物事から情報を得るのに五感をフル稼働する習慣がついているため、容易にイマジネーションを働かせられます。
小説を読んで登場人物の髪型や服装を想像したり、本の主題をあれこれ考えたりできるのも感性豊かな子どもの特徴です。実際に目にする情報以外の世界をイメージできるといえるでしょう。
人とは違うセンスを持っている
五感を研ぎ澄まし多様な見方で情報を得る子どもは、ほかの人とは違うセンスの持ち主です。この背景には、固定観念にとらわれない姿勢が関係しているでしょう。
感性があまり豊かでない人は物事を理解するのに「常識」から入ります。違う視点で物事を見るのが難しく、何か変化が欲しいときにアイデアを出せない傾向にあります。
つまり「感性が豊かな子ども」とは、自分の五感を通して物事をとらえるのに慣れている子どもを指し、ほかの人が思い浮かばないような発想をするといえるでしょう。
喜怒哀楽に忠実である
喜怒哀楽に忠実である点も感性豊かな人の特徴です。「喜怒哀楽に忠実」とは、思ったまま表現したり行動したりできることを指します。
たとえば、下記のように表現する子どもは感性が豊かであるといえるでしょう。
- 試合に勝ったときに「やったー!」と笑顔で叫ぶ
- 友達に嫌なことをされたときに「やめて!」と伝える
- ドラマを見て感動したときに涙を流す
- 大好きなブランコを満面の笑みで揺らす
このように豊かな感性を持つ子どもとは、日常生活の何気ない瞬間でも感情を素直に表現する子どもを指すといえます。
優しいコミュニケーションができる
感性が豊かな子どもは、相手にとって優しいコミュニケーションができます。優しいコミュニケーションとは、相手を理解するやり取りを示します。
相手の話す言葉だけでなく表情や声のトーンから話す人の心を敏感に感じ取るのが、豊かな感性の持ち主です。つまり、感性が豊かであれば、相手の言葉の背景にある本音を読み取りながら会話する力に優れているといえるでしょう。
感性から生まれる優しいコミュニケーションによって、周囲に友達が集まり人間関係を良好に保てます。
感性は人それぞれ。まずは子どもの「らしさ」を尊重して

感性は人それぞれです。感性を育てるためには、まずは“その子らしさ”に目を向けなければなりません。
紹介した「豊かな感性を持つ子ども」の特徴をある種の固定観念として受け止めれば、子どもの「らしさ」に気づけない可能性があるでしょう。「らしさ」を大切にするとは、ほかの子どもと比べずに子どものありのままを認めることを指すのです。
子どもの五感やセンスは誰ひとりとして同じではなく「感性=個性」だといえるでしょう。感性を磨くには「違うのが良い」と考え、「らしさ」を尊重する姿勢が大切です。
保護者はほかの子どもとは違う言葉や発想、行動などを認めることから始めます。子どもを全面的に認めてこそ、感性が育つととらえましょう。
子どもの感性を磨く方法11選

感性を磨くには、可能な限り多様な経験を重ねる必要があります。経験を通して自分の感覚が研ぎ澄まされれば、その子らしい表現が可能で感性豊かな子どもに成長するでしょう。
特に幼児期は、感性が育まれる大事な時期といわれます。日常とは異なる体験をさせたりさまざまな人々と交流させたりする機会は、感性を育てる上で重要でしょう。
ここでは子どもの感性を磨く方法として10個紹介します。日々の生活に少しずつ取り入れてみてください。
できる限り新しい場所に連れて行く
今までとは異なる場所で新しい体験をするのはドキドキしますね。ドキドキは、子どもの感性に刺激を与え好奇心をかきたてます。
感性を育てたい場合は、同じ場所に限定せず少し違う場所に出かけるとよいでしょう。いつもと違うものを見たり触れたりするのは、子どもの五感に良い刺激となり感性の育成に役立ちます。
子どもが新しい発見や驚きを素直に表現したときは、保護者も「本当、びっくりしたね」と共感的な姿勢で受け止めると感性をより一層磨けるでしょう。
シミュレーション要素が高い遊びを取り入れる
感性を豊かに育みたい場合は、シミュレーション要素の高い遊びを取り入れると効果があります。その理由は、見えるものから次の状況を推測する想像力を養えるためです。
例えばシミュレーションゲームは、現実ではありえない出来事を想定した場面のなかで楽しむ遊びで、子どものイマジネーションをかきたてるでしょう。
「ゲーム以外でおすすめの遊びとは?」と聞かれた場合は、ままごとや〇〇ごっこといった遊びをおすすめします。ごっこ遊びは自分を誰かに見立てたり自分を取り巻く状況をイメージしたりするため、子どもの想像力を育みながら感性を磨けます。
クリエイティブ要素が高い遊びを取り入れる
クリエイティブ要素の高い遊びとは、五感を使いながらアイデアを形にしていく遊びを指します。感性を磨きたい場合は、次のような遊びを取り入れてみましょう。
- ブロック遊び
- お絵かき
- 折り紙
- 粘土遊び
- 工作
いずれも視覚や触覚などを使って楽しむ遊びで感性を豊かに育みます。そのほか地域によっては、粘土や段ボールを使ってダイナミックに創作するイベントも開かれています。親子で一緒に参加して感性をさらに磨いていきましょう。
子どもの心と体にゆとりのある環境をつくる
子どもの感性を育む場合に親が意識したいのは、子どもの心と体にゆとりをもたせることです。心と体にゆとりがあれば安心して、新しい世界に飛び込んでいけます。また、美しいものに感動できるのもゆとりがあってこそです。
心と体にゆとりがなければ、出会った人や事物の様子や変化にまったく気づかず感性そのものを育てられません。ゆとりがないと感じる場合は「感性を育てなければ」と思い込まず、まずは親子の時間をとって子どもに安心感をもたせましょう。
子どもの心が満たされ穏やかになれば感性を磨くチャンスとなります。
保護者は時間にゆとりを持ったスケジュールを組む
感性を磨くために「時間にゆとりをもったスケジュールを組む」とは、子どもが焦ることなくじっくりと物事に対応できる時間や場を設定することを指します。
子どもが安心感をもってゆったりと楽しめる状況をつくるには、やはり保護者の協力がなければ難しいでしょう。保護者が忙しくて気もちのゆとりのないときは、支度が遅いと注意したり慌てさせたりする可能性があります。
このような状況下では子どもの感性を磨けません。感性を育むとは、「急いで」といった言葉を発する必要のないようスケジュールを組み、子どもにゆとりをもたせる姿勢ととらえましょう。
親子でネイチャーアクティビティを楽しむ
ネイチャーアクティビティとは、自然のなかで体験活動をすることを指します。親子で一緒にアクティビティを楽しむ時間は子どもの感性を磨くのに役立つでしょう。
ネイチャーアクティビティは、感性を磨く上で下記のようなメリットがあります。
- 五感を育てる
- 心と体の調子を整える
- 自尊心を育む
3つの要素は子どもの感性を磨く上で重要です。また、親子一緒にネイチャーアクティビティを楽しむのは、子どもの持つ感性に気づき認めるチャンスになるでしょう。
積極的にアート作品と触れ合う
子どものころからアート作品に触れ合うのは、ふだんとは異なる世界観を味わい、感性に良い刺激を与えるため表現力を磨くためにも重要です。
大人がアート作品を見る場合、固定観念にとらわれる場合があります。しかし子どもは素直であるため、初めて目にするアート作品に圧倒されたり自由な視点で感想を述べたりするでしょう。
まさに感性が放たれた瞬間であり、どのような感想を持つにしてもアート作品に触れるのは子どもの感性をさらに磨くチャンスといえます。
学校と家庭以外でコミュニティを広げる
コミュニティとは、複数の人々が集まって形成される共同社会を指します。感性を豊かにするには、学校と家庭以外の人々と触れ合う機会をつくりましょう。日常に変化をもたせると新しい見方を得られ子どもの感性に刺激を与えられます。
感性を豊かに育てるには、例えば次のような取り組みをしてみましょう。
- 習い事を始めてみる
- 地域行事に参加する
- ほかの地域のイベントに参加する
さまざまな人との出会いによって多様な価値観に触れられるため、さらに感性を磨けます。ときには外国人との交流イベントに参加するのも良いでしょう。
結果よりもプロセスを認める
子どもの感性を磨きたいと思えば、結果よりもプロセスを認めるようにしましょう。結果よりもプロセスを認めるとは、「どのように感じたのか」に着目する姿勢を指します。
また、大人がいつも先回りした行動をとれば、感性をうまく育てられません。たとえばアート作品を見て「この絵はきれいでしょ」と結論を出してしまう行動です。
子どもが感性を研ぎ澄ましているプロセスを邪魔してはなりません。感性を磨くには、子どもが感じるプロセスを尊重し子どもの素直な反応を認めましょう。
子どもと対等な立場で物事を楽しむ
子どもと対等な立場で物事を楽しむとは、各活動をする際に子どもと同じように楽しむことを指します。逆に教育的な言葉かけをしては子どもの感性を育てられないでしょう。
親子で工作をするときに「この切り方はちょっと雑だね、もっときれいに切った方がいいよ」と評価してはいけません。対等な目線で「お母さんは、こうしてみようっと…」のように保護者も工作を楽しむ姿を見せれば子どもの感性を刺激するでしょう。
つまり感性を豊かにしたい場合、違いを紹介し合う姿勢が重要なのです。違いを認め双方の良さに気づかせる方が、子どもの感性や表現力をさらに磨けるでしょう。
動物・植物に触れる機会を増やす
動物の飼育や植物の栽培は子どもの感性を磨く1つの方法としておすすめです。自宅で動物を飼うことが難しい場合は、公園で昆虫に触れてみる、動物園で動物を見るだけでもさまざまな思考を刺激し、新たな発見やワクワクが見つかるかもしれません。
家庭菜園や鉢植えで花を育ててみたり、観葉植物に水をやったりすることもおすすめ。育てた野菜を料理に取り入れることも、子どもの感性を磨くことにつながるでしょう。
感性が豊かな子どもが注意したいポイント

感性が豊かな子どもにはいくつか注意したい点があります。注意したい点とは、豊かな感性をもつがゆえ、子どもが時に自分をコントロールできなくなることを指します。子どもが持つ感性を大切に育てるには、保護者が子どもが混乱する要素を理解し適切に支援する必要があるでしょう。
ここでは、子どもに起こりうるネガティブな部分を紹介しながら、解決に関わる視点を解説します。
必要以上に傷つきやすい
感性が豊かな子どもは、必要以上に傷つきやすい側面をもっています。この背景に環境に対する感度が高い点が挙げられるでしょう。見えない部分も含めて一気に自分のなかに取り込んでしまうのです。
せっかく素晴らしい感性を持っているのに、他者のひと言で自信を失ったり逆に攻撃的になったりして人に誤解されてしまいます。
この場面で必要な保護者の手立てとは、傷ついたときに温かくサポートすることです。共感してくれる人がそばにいるだけで、感性豊かな子どもは安心して次のステップに進めるでしょう。
想像力が高く、臆病になりやすい
感性豊かな子どもは想像力がとても高いため、他者の心や起こりうる状況を想定できます。コミュニケーションを円滑にしたりリスクを予期できたりする良さはありますが、臆病になりやすいかもしれません。
その理由は「もしも先生に〇〇といったら怒られるだろう」「〇〇をしたらうまくいかないかもしれない」といった感じで未来を予測し過ぎてしまうためです。まずは保護者が話を聞いて安心させましょう。
感性を育てようとさまざまな経験をさせる際は、親子一緒に参加して温かく励ましながら背中を押してあげるのが有効です。
現実離れした発言をしてしまうことがある
「現実離れした発言」とは、固定観念にとらわれず自分の気もちを正直に伝えることを指します。感性が育っている子どもであれば、ときに現実離れした発言をして周囲をやきもきさせるケースがあるでしょう。
その場にいる保護者が慌てて本人はケロッとしているかもしれません。ただ、ここで頭ごなしに「だめでしょ!」と叱るのではなく、相手や状況に応じて言葉を選んで使う必要性を伝えましょう。
感性豊かな子どもはなかなか理解できないかもしれませんが、気長に伝えていく姿勢が大切です。
子どもの感性が鈍ってしまう5つのNG行動

子どもの感性を磨く上で保護者がしてはならないNG行動があります。前述のように感性豊かな子どもは時に傷ついたり臆病になったりするため、必要以上にプレッシャーをかけないようにしましょう。
また、保護者が「絶対ダメ!」と語気を強めたり圧力をかけたりするのもNG行動です。感性そのものがデリケートであるため、圧力をかけられれば一気にしぼんでしまいます。豊かな感性を育てるには保護者の姿勢は重要です。
ここでは子どもの感性が鈍ってしまうNG行動として5つ紹介します。
必要以上にプレッシャーをかける
保護者が何気に発する「ダメ!」「違うでしょ?」といった言葉は、子どもに過度のプレッシャーをかけます。ここでのプレッシャーとは、子どもの自由な言動を阻害し感性を鈍らせる働きかけを指します。
命を危険にさらしたり人を傷つけたりするとき以外、何でもかんでも否定するのは感性を鈍らせてしまうでしょう。もともと感性が豊かな子どもであっても、親から注意され続ければ自分の行動に制限をかけるようになります。
子どもを抑えるのではなく、ありのままの感性を受け止める姿勢が大切です。
誰にも迷惑をかけないようなことを禁止する
日本人は「人に迷惑をかけない」ことを子どもに教えますが、求め過ぎれば子どもは生きづらくなります。押さえつけられて育った子どもは、大人になって迷惑をかけてしまうかもしれません。
豊かな感性を育むには、子どもの言動をすべて制御するのではなく“迷惑をかけてもいい”といった見方も必要でしょう。子どもは素直に自分を表現できてこそ、人と本音で語り合ったり力を合わせたりする大切さを学ぶのです。
たとえば海外のように「人に迷惑をかけるのは致し方ないことで、だからこそ共に助け合うのが大切」といった考え方は感性を育てる際に参考になります。
無言の圧をかける
無言の圧をかけるとは、保護者が子どもを否定していることを指しています。子どもの感性だけでなく人格形成の上でもよくありません。
保護者が「〇〇すべき」といった考え方を子どもに押し付けるのと同様に、子どもに「自分のことは受け入れられていない」といった感情を抱かせるでしょう。自尊心さえ失ってしまいます。
感性を育むには、子どもを肯定し寄り添う姿勢が大切です。
子どもの大切なものを人質にとる言動
子どもの大切なものを人質にとる言動とは、保護者の思うような行動をとらない場合「〇〇しないと大事な▢▢をさせないよ(あげないよ)」といった圧力をかける言動を指します。
大切なものをとられそうになれば、子どもは自分の言動を制御するしかありません。これでは自由に感情を表したりありのままの感性で行動したりするのは難しくなります。
豊かな感性を育てるには、大切なものとの交換条件で言動をコントロールしないようにしましょう。
友達付き合いを限定する
感性を豊かにする場合、できる限り多くの経験や人とのつながりをもたせる必要があります。逆に友達付き合いを大人の価値観で限定するのは、大人の価値観によるもので子どもの目線に立っていません。
子どもの自由度をなくしてしまい、豊かな感性を育てるのは難しくなります。
子どもに危害が加えられたりトラブルになったりする恐れがある場合であっても、一方的に保護者の考えを押し付けるのはやめましょう。子どもと対等な立場で話し合い、子どもに考えさせた方が感性を育てるにも効果があります。
安全を守りつつ、子どもの発想力を引き出す教育が大切

安心・安全な環境で子どもが過ごせるように正しい道を示すのは保護者の責任といえます。子どもの「らしさ」を大切にするとはいえ、危ない遊びをしたり友達や自分を傷つけたりする言動はしっかり注意しなければなりません。
つまり「安全を守りつつ、子どもの発想力を引き出す教育」が大切なのです。安全かつ想像力を引き出す視点で行う教育とは、次の視点で行われる教育を指します。
- 子どもの行動や気もちを認める
- 子どもの主体性を大切にする
- 寛容さを保ち、見守る
- 必要なときにはサポートする
この視点で育てると、安全を保ちつつ子どもの発想力を引き出しながら感性豊かな子どもに育てられるでしょう。また、子どもに助けが必要な場合も高圧的にならずに適切な対応ができます。
『Wonder Code』で、英語やロボットを通して感性を磨こう

予測不可能な時代においては、感性が豊かである方が活躍の場が広がると考えていいでしょう。そのために、保護者が子どもの感性を大切に育てる姿勢をもち、適切な対応をする必要があります。
時間にゆとりをもたせながら、子どもと一緒に遊びや出会いを楽しむ姿勢が大切です。また五感に刺激を与える体験を多く設定するのは、子どもの感性を豊かにし発想力をさらに広げるでしょう。
体験とは今回紹介した美術館訪問やネイチャーアクティビティなどを指しますが、それだけではありません。英語やロボットなどの新しい出会いを通して感性を磨くこともできます。
『Wonder Code』は、感性を育てるためのプログラムを取り入れています。記事を読んで興味をもたれた保護者様は、この機会にお問い合わせまでご連絡ください。