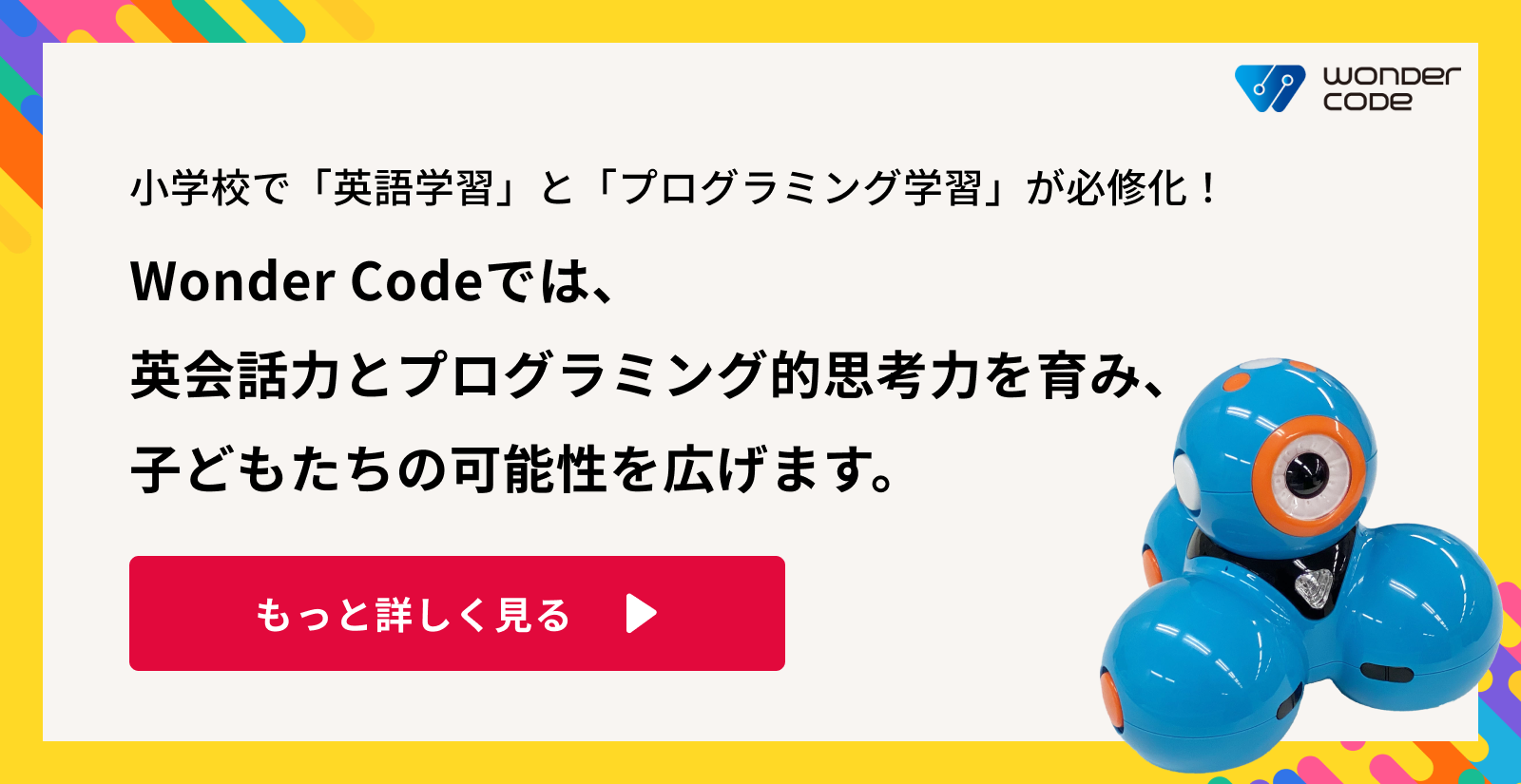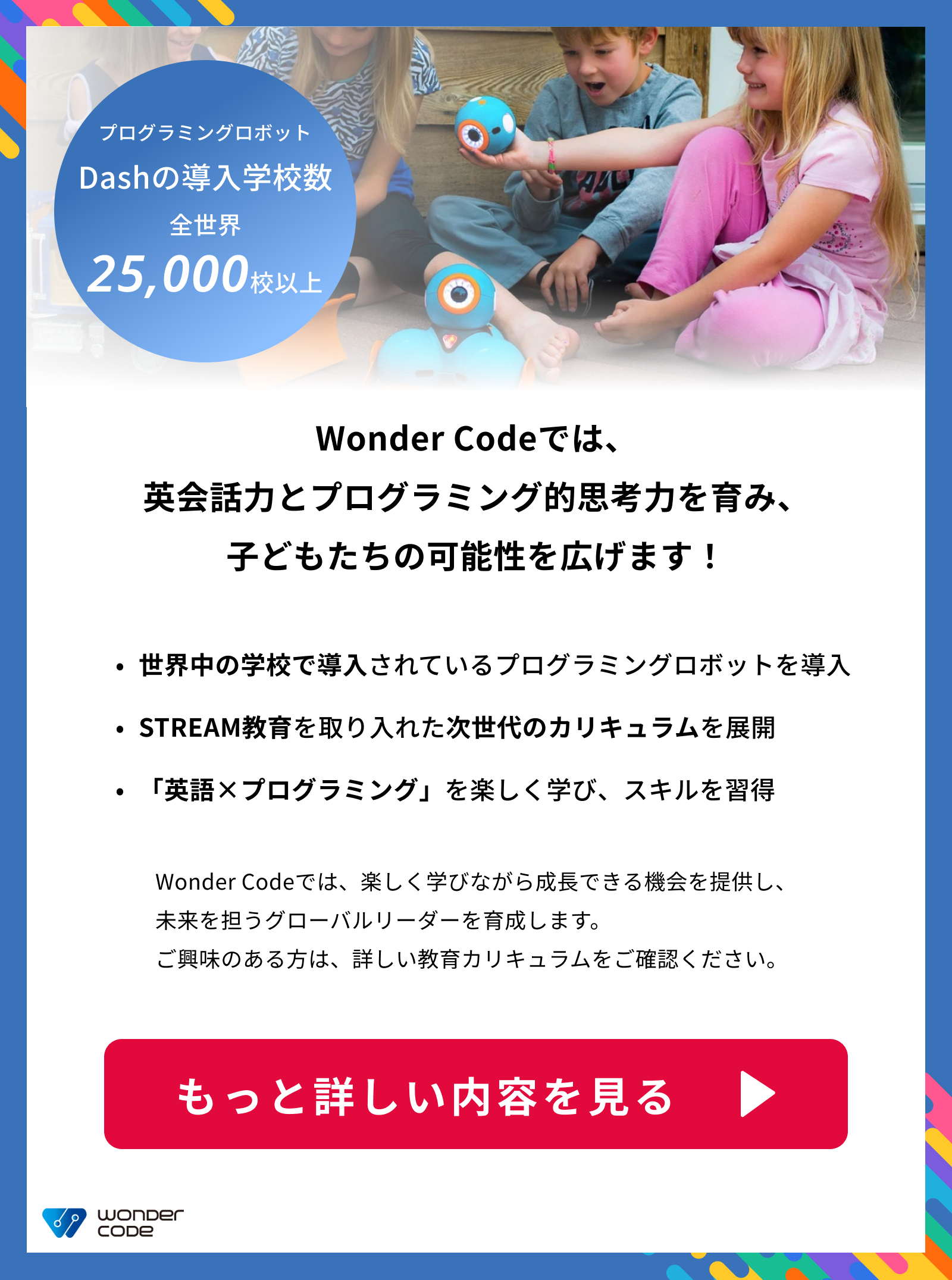【この記事の目次】
小学校の算数で学ぶ内容は?保護者ができることを考えよう

小学生の算数では、加減乗除(たし算やひき算、かけ算、わり算)といった基本的な計算方法を学びます。また、時間や長さ、面積、体積などの測定単位の理解や、分数や小数など数値の学習も必要です。
保護者が小学生に算数を教える場合の取り組み方法には、次のようなものがあります。
- 日常生活で算数に関する問題を見つけて一緒に考える
- 小学生向けの算数テキストを用意して解かせる
- 算数専門の家庭教師に依頼する
いずれにしても子どもの算数力を向上させるには、保護者が算数の学習内容を把握しつつ継続的にサポートしていく姿勢が重要です。
今回は小学生が習得すべき学習内容を確認したうえで、保護者がどのようにサポートしたらよいのかを解説します。
【学年別】小学生の算数のおもなカリキュラム

小学生の算数は、あらかじめ決められたカリキュラムに基づいて教わります。算数のカリキュラムは学年別に分かれており、算数の系統性や発達段階を加味しながら、計画的に学びが進むように工夫されているといえるでしょう。
ここでは、小学生が六年間かけて学ぶ算数カリキュラムの概要を紹介します。学年ごとに到達させたい算数の内容を把握して、家庭におけるサポートに取り入れていきましょう。
一年生の算数の内容
小学一年生の算数は、たし算とひき算の習得がおもな学習内容となります。一年生の学習内容は以下のとおりです。
- たし算(繰り上がり含む)
- ひき算(繰り下がり含む)
- 数字の大小の関係
- 数の並べ替え
- 時計の読み方
- お金の数え方
- 基本的な図形認識
入学当初は算数の学習で使う用具の説明を受けながら、学習と遊びを融合させた授業が展開されます。ただ、1年間で教わる内容は意外に多く、家庭でのサポートが不十分だと、小学生になったとたんに算数嫌いになるかもしれません。
二年生の算数の内容
小学二年生になると、一年生での学びを深めたり新しい算数の概念を学んだりします。おもな算数の学習内容は次のとおりです。
- たし算やひき算の筆算
- かけ算九九
- 長さ
- かさ
- 図形の概念
- 分数の基礎
- 時計の読み方や時間の計算
すべて算数の土台となる学習ですが、覚えることが増えて負担を感じる小学生もいるでしょう。とくにかけ算九九の習得は覚える数字パターンが多く、継続して練習しなければ身につきません。
保護者自身も、ねばり強く家庭でサポートする必要があります。
三年生の算数の内容
小学三年生の算数では、わり算や小数が新たに加わり二年生で学んだ基礎をもとに分数も学びます。以下の内容が、三年生のおもな学習内容です。
- 難易度の高いたし算とひき算、かけ算
- わり算と筆算の仕方
- 小数の使い方
- 分数の使い方と分数のたし算(ひき算)
- そろばん
- 長さや重さの単位
- 時間や時刻の求め方
- 二等辺三角形と正三角形、角
- 円と球
- 表やグラフ
既習事項に加えて、わり算や面積・体積の測定、円や球などの新たな図形の概念が入るなど算数の難易度が高まります。
小学生が身につけるべき基礎的な内容のほか、文章問題を説く論理的思考力や空間認識能力など数学的なスキルが求められます。算数力の定着に向けて家庭学習で補う必要があるでしょう。
四年生の算数の内容
小学四年生になると抽象的概念を含む内容が授業で増えるため、算数につまずく小学生が増えるかもしれません。抽象的概念とは、算数の問題で問われる場面をイメージしにくい考えを指します。
四年生で学ぶ算数の学習内容には、以下のように今までとは異なる概念や方法が含まれます。
- 角度と大きさ(三角定規や分度器)
- 2ケタ以上の数字を1ケタ(2ケタ)で割る筆算
- 1億をこえる数
- 折れ線グラフをかく
- 垂直と平行の概念
- さまざまな四角形
- 小数の仕組みや計算
- 四則計算の順番
- がい数
- 面積の計算
- 直方体と立方体
このように、算数の学習内容は徐々に難しくなり、計算問題が正確にできるだけでは太刀打ちできません。四年生になって算数に苦手意識をもつ子どもが多くなるといわれるため、家庭学習で補う必要があります。
五年生の算数の内容
小学校五年生になると、四年生よりもさらに算数の難易度が上がります。実際の学習内容は以下のとおりです。
- 小数のかけ算やわり算
- 直方体と立方体の体積(展開図も使用)
- 比例
- 単位や割合、人口密度
- 百分率や歩合
- 整数と分数
- 偶数と奇数
- 倍数と公倍数
- 約数と公約数
- 約分と通分
- 分数と計算
- 多角形や円柱、角柱
- 変わり方
- 〇や△を使った計算
上記の内容から、小学五年生の算数がいかに難しいかがわかります。中学校で学ぶ内容の基礎となる部分が多くあるため、基礎が身についていないとまったく解けません。
内容によっては家庭で四年生以前の算数を復習させる必要があるでしょう。
六年生の算数の内容
五年生の学習と同様に、六年生の算数ではさまざまな計算方法や図形の概念を学習します。小学生が六年間で学ぶべき算数の内容を総復習するとともに、中学へ向けての基礎固めを確実に行う必要があるでしょう。
六年生の算数の内容は以下のとおりです。
- 分数のかけ算やわり算
- 逆数の考え方
- XやYを使った数式
- 図形の拡大や縮小、対称性
- 速さ
- 比例と反比例
- 円の面積や立体の体積
- 量の単位
六年生の算数では、小学生が身につけるべき基本的な内容を断片的にではなく関連付けながら問題を解く力が問われます。単に公式を覚えるだけでは課題を解決できないでしょう。
また、文章問題を読んで状況をイメージしたり、問題を解決するために必要な要素や順番を考えたりする力も必要なのです。
小学生の算数を家庭教育でサポートするポイント

家庭において小学生が算数を学習するためには、学習習慣や環境を整えることが大切です。また、算数と関連する場面とつなげて考えさせたりレベルに合わせてテキストを選んだりするなど、保護者が適切にサポートしなければなりません。
小学生が算数を好きになり得意教科にしていくうえでは、以下の3つの力が必要です。
- 計算力
- 思考力
- 表現力
小学生にとって「計算力」は、算数の力を伸ばすために重要な力です。計算力があれば算数の問題を正確に、かつスピーディーに解くことができます。
「思考力」は算数の問題を多面的に理解し、複数の解法を思いついたり解法のなかからもっとも効率的な解き方を導き出したりする際に必要です。
3つめの「表現力」とは、算数でいえば自分の考えを式や図などを使って表現する力を指します。数的センスに優れている子どもは難なくやり遂げるでしょう。ただ、思考の過程を丁寧に表現する力を養っていたほうが算数の力をさらに伸ばせます。
家庭で小学生に算数を学習させる場合、保護者が子どもの様子を観察し3つの力を意識してサポートすれば、子どもの算数力は少しずつ向上するでしょう。参考
算数を好きになるためには、計算力を身につけよう

先ほど紹介した算数の3つの力はすべて、地道に取り組むことで成果があらわれるものです。今回は計算力を取り上げ、小学生がどのように計算力を身につけられるか解説します。
計算は決まったパターンを習得すれば、練習を積み重ねることで力がつく分野といえるでしょう。毎日10分でも継続して取り組むと、計算のスピードや正確性が上がってきます。
たとえば毎日宿題に出されるドリル演習を「ただやる」のではなく、タイムと点数を表やグラフなどの記録に残すのです。小学生の子どもは日に日に伸びる記録を見て自信をもち、モチベーションを向上させるでしょう。
あるいは、一緒に買い物へ行って算数とつなげて計算する機会は、小学生に実感をともなった数的感覚を養わせるのに役立ちます。
計算力がついてきたところで、少しずつ応用問題に挑戦させましょう。たとえば難しい算数の問題を解く場合、保護者は絵や図に表して考えやすくしたり、思考の過程を式や言葉で表現させたりします。子どもはその過程で思考力と表現力を身につけながら、得意な計算力で答えを正しく導き出せるでしょう。
こうして算数的な場面でさまざまな経験をさせながら地道に算数の力を伸ばしていくのです。小学生の子どもが算数に興味をもち好きになってくれば、進んで難しい問題に挑戦し始めるでしょう。
算数に必要な論理的思考力を身につけるなら『Wonder Code』

小学生は六年間で計算や図形、数学的な概念など多角的に学びます。しかし、途中で挫折してしまい「算数は苦手」と思う小学生がいるのも事実でしょう。
小学生が算数を好きに、そして得意になるためには計算力や思考力、表現力を育てていかなければなりません。計算力をつける学習過程で思考力や表現力を意識する姿勢は重要です。
3つの力をしっかり習得すれば、予測不可能な時代を生き抜くための強みになるでしょう。
算数に必要な論理的思考力を身につけるには『WonderCode』のカリキュラムが有効です。小学生のうちに子どもが算数を好きになり、自信をもって学び続けられるようにするためにも、ぜひ『Wonder Code』にお問い合わせください。